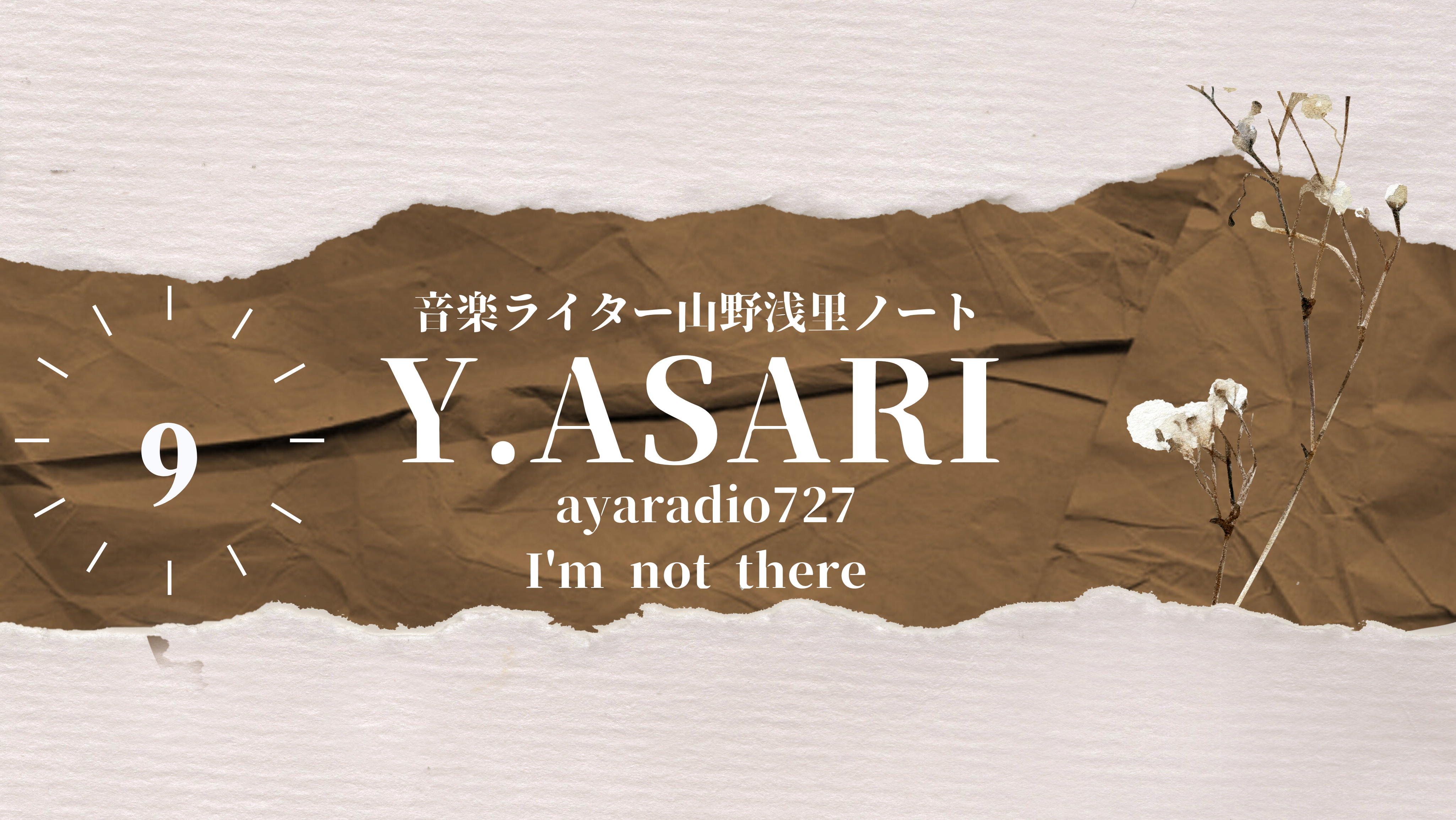幸運にも音楽ライターのASARIさんがayaradio727の音楽を取り上げてくださることになりました。
§I’m not there
ASARI
この楽曲はまずayaradio727自身による解説に触れたい。曰く「自分の中にあるなんともいえない気持ちを音楽で表していくこと」に意味がある、「歌いたいことがまず最初にあって、そこにコードやメロディーを後からつけていく」など、自覚的且つクリエイティビティと密接なポイントが明らかにされている。こうした解説、つまり創造に対する姿勢を明らかにするか、あるいは覆い隠すかというのは作者が培った美学や造詣によっても異なるだろうし、あるいはひとりの作家の中でも作品によって時期によって変遷はあろう。しかしayaradio727作品は今の所概ね一貫性をもってこの自らの解説の通りではないかと感じる。
その上で楽曲の幅やテーマが徐々に広がっていくのがこの頃の作品だ。この曲で際立つのは中間部のラップだろう。それはヒップホップマナーに依らず、ポエトリーリディングに近いスタイルで表現される。この点は重要で、すなわち軸足をもちつつその範囲で少しづつ幅を広げていくという点で連続性を保ちながら生活圏を広げていくようにも思える慎重な試みだ。すなわちスタイルの変更ではなく、むしろ深化であることに冒頭の本人による解説や言葉の連なりと想いが重なる。
楽曲はピアノを軸にしてリズムトラックがややフロントに置かれた、それでいて静かな冒頭から始まる。印象的なのは「もう」が3回繰り返される箇所で、MVはそこで遊ばなくなって久しいはずの公園が映し出されており、しかしそれはノスタルジアよりも悲痛さが上回るようにも感じられる。このシーンを踏まえての上述の中間部のラップだ。そこで映し出されるシーンは目線が少しだけ変わる。そしてある種の痛みに対する強い感情がぶつけられるが表現方法は先に記した通りだ。
筆者が注目したのはこのラップの後の展開だ。受け入れつつも受け入れられない状況があり、MVはいったん暗転。ここでまさに今の目線を今歌うというアプローチに切り替わる。そして「もう」が3回繰り返された冒頭に暗転はなかったことにここで気づく。それはまるで一本のロードムービーのようだ。今に至るまでの時間軸と感情の揺らぎがシーンを変えつつスタイルを変えず1曲に収まり、聴き手は聴き手の想いの中で楽曲を再構築する。どこにもっとも余韻を感じるかはその時のフィーリング次第だ。楽曲に幅があるというのはまさにそういう事ではないかと思う。
この曲のMVはこちらです↓

この曲は自分でも面白い曲だと思っていて、ここで歌っている心情はシリアスなのですが、思い切って英語でのラップを取り入れたりラップ後のパートにはシアトリカルな部分も展開されたり、と、ASARIさんのレビューのとおりに、どんなふうに感じるかはリスナーのその時のフィーリング次第で変わるような、少し風変わりな1曲です。MVの風景も身近な景色なのに心情を語っていてお気に入りです。
ASARIさんのNoteはこちらです↓